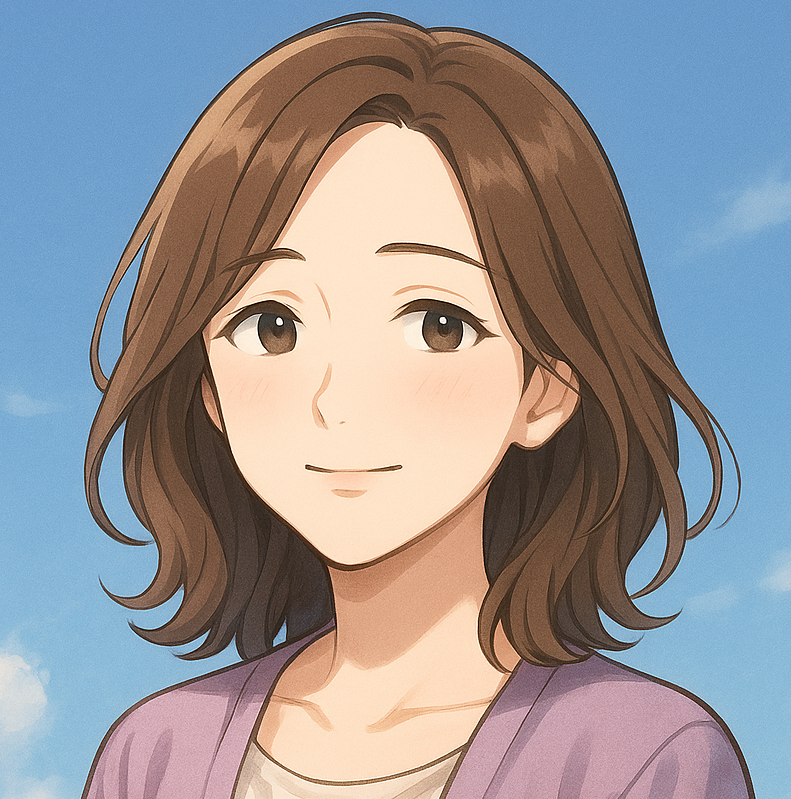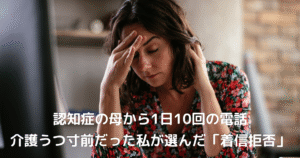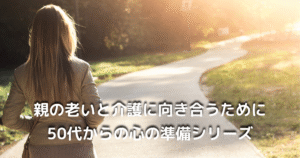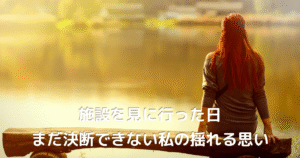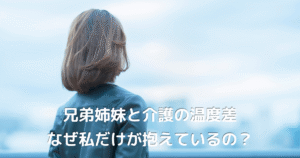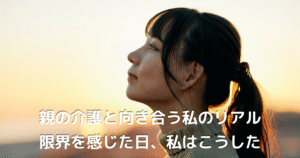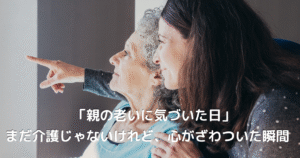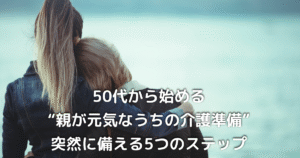【認知症の始まり】母の変化に気づいた日と最初の戸惑い
私の母に最初の異変が現れたのは、まだ「歳のせいかな」と軽く流していた頃でした。何度も同じことを尋ねてきたり、料理の手順を忘れたり。最初は「疲れているのだろう」と思い込もうとしましたが、違和感は日々募っていきました。
「なんでそんなこともわからないの?」と、つい声を荒げた日もありました。ですが、そう問い詰めるたびに、母の表情は不安に曇り、ますます混乱していくようでした。そこでようやく、私は気づいたのです。普通の対応では、もう届かないのだということに。
認知症の母に“普通の対応”が通じなかった理由
認知症という病は、単なる「もの忘れ」とは異なります。脳の機能が少しずつ失われていく病気であり、その人の「らしさ」や「社会性」までもがゆっくりと薄れていきます。
たとえば、「なんで忘れるの?」「さっき言ったでしょ?」といった言葉は、認知症の方には通用しません。それどころか、相手を傷つけ、さらに混乱させてしまいます。
私たちが「常識」と思っている対応が、むしろ症状を悪化させてしまうのです。
母は、かつては自信に満ちたしっかり者でした。しかし、認知症が進むにつれ、その強さは影をひそめ、子どものように不安そうな目をするようになりました。その姿を見るのが、何よりつらかったのです。
【介護の現実】認知症の母に振り回される日々と心の限界
介護は、想像以上に体力と精神力を消耗します。特に認知症の介護は、日常のすべてが「予測不能」の連続です。
母は食事を済ませた直後に「まだ食べていない」と言い、薬を飲んだのに「飲んでいない」と怒り出すこともありました。最初は何度でも説明しようと努力していましたが、次第に私の方が限界に近づいていきました。
「自分がしっかりしなければ」という思いが、いつの間にか私の心を締めつけていたのです。けれど、がんばればがんばるほど、疲れや孤独感ばかりが募り、気づけば自分の感情を抑えることさえ難しくなっていました。
【子どもに戻った母と向き合う】私がたどった道と変わる関係
認知症が進むにつれ、母はまるで子どものようになっていきました。できないことが増え、感情の起伏が激しくなり、「帰る」と言って玄関から出ようとしたり、「お父さんお母さん兄弟に会いたい」と涙を流したり。
そんな母に私は、最初は戸惑い、苛立ち、時には強く突き放してしまったときもあります。だけど、ある日ふと思ったのです。これはもう”親子”ではなく、”赤ちゃんと育てる側”のような関係なんだ、と。
私は母を守る人になろうと決めました。正解は分からないけれど、少しずつ、母の目線に立つことを覚えていこうと思ったのです。母が求めていたのは、愛情と安心でした。
おやつを一緒に食べる時間、昔話を聞く時間、手をつなぐ時間。その一つひとつが、母との関係を再構築する鍵になりました。
【がんばりすぎた介護の代償】心が壊れかけた私が学んだこと
「私がしっかりしなきゃ」「誰も代わってくれないから」と自分に言い聞かせて頑張ってきたけれど、それは長続きしません。
頑張ることは大切。でも、自分の心が壊れてしまったら元も子もありません。介護はマラソンのようなもの。全力疾走では途中で倒れてしまう。
介護うつという言葉を初めて知ったのは、自分がまさにその状態になってからでした。頭痛、肩こり、不眠、過食。心が悲鳴を上げていたんですね。
そんなとき、私は「手を抜く勇気」を持つことにしました。できない日はできないと認める。逃げたい日は逃げてもいい。そう思うことで、少しずつ心に余白ができていったのです。私は自分自身に気づくのです。「私は、母のために頑張っていたけど、自分を全然大切にしていなかったんだ」と。
【ひとりでは限界】認知症の母と暮らす日々に必要だった支えとは?
私ひとりではどうにもならない。そう痛感したのは、母が夜中に家を出て警察に保護された日でした。
そこから、地域包括支援センターやケアマネジャーとつながり、デイサービスやショートステイも使うようになった。「助けてください」と言ったら、意外とたくさんの手が差し伸べられていることに気づきました。
支援を受けることは甘えではない。むしろ、それが「長く続けるための知恵」だと今では思う。私はようやく人間らしく暮らせるようになった感じがします。
【距離を取ることの大切さ】向き合いすぎない介護法
向き合いすぎると、壊れてしまう。だから、あえて”距離を取る”ことを選んだ私。
仕事もあるので、休みの日には、兄や甥に代わってもらい、一週間に一度は、介護と向き合わない一日を設けました。
介護は愛情だけでは乗り切れない。冷たく聞こえるかもしれないけれど、自分を守るためには”離れる勇気”も必要なのだと学んだ。認知症で子ども返りした母にどう向き合う?私の体験談
母はかつて、厳しくも頼れる存在でした。自分の意見をしっかりと持ち、周囲の人間にも遠慮なく物を言う、そんな芯の強さがありました。しかし、認知症が進行するにつれ、その強気だった母が、まるで子どものように甘えたり、気分によって怒ったり泣いたりするようになったのです。
最初のころは、「どうしてこんなにわがままになったのだろう?」と戸惑いました。でも、あるとき主治医から「認知症の方は感情の抑制が難しくなることがあります」と聞かされ、納得しました。
それ以降、私は、母親ではなく、子どものような存在としての母と接する覚悟を決めました。年老いた母が子どものように不安を抱えているなら、私はその不安を包み込める存在になろう。そう思ったのです。
がんばりすぎる介護は危険!心を壊す前に気づくべきこと
「自分が頑張ればなんとかなる」と思っていた私は、毎日気を張り詰めて、介護に向き合っていました。しかし、ある日ふと、自分の顔がまるで感情を失った仮面のように感じられたのです。
鏡の中にいたのは、笑わなくなった私でした。
介護は、がんばりすぎると心を壊します。
自分の感情を押し殺し、無理を続ければ、やがて限界が来るのは当然のことです。私はそのことを、身をもって実感しました。
それ以来、「介護する自分のケア」も同じくらい大切だと考えるようになりました。認知症介護はマラソンのようなものです。息切れしないためには、自分のペースで走ること、そして立ち止まることも必要なのです。
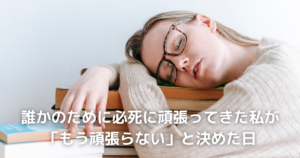
認知症の母との暮らしに必要な支援とは?
介護を一人で抱えると、次第に視野が狭くなります。周囲の助けを求めることに罪悪感を覚え、「自分でやらなければいけない」と思い込んでしまうのです。
しかし、認知症介護は一人で抱えるには、あまりにも重すぎる現実です。私は地域包括支援センターに相談し、介護認定を受け、訪問介護やデイサービスといった制度を利用するようになりました。
最初は他人に任せることに抵抗がありましたが、支援を受けることで、母にも私にも笑顔が戻ったのです。プロの手を借りることは、けっして「手抜き」ではありません。むしろ、お互いの尊厳を守るために必要な選択だと感じています。
認知症の母と距離を取る大切さ:向き合いすぎない介護法
「親なのだから、最後まで付き添わなければ」と思い詰める方も多いかもしれません。私も、かつてはそうでした。
けれど、四六時中介護のことばかり考えていては、自分の人生がなくなってしまいます。介護の質を保つためには、あえて“距離”を取ることが必要な場面もあると気づいたのです。
たとえば私は、週に1日は母と物理的に離れる「ひとり時間」を持つようにしました。本を読んだり、散歩をしたり、好きなカフェで過ごしたり。そんな些細な時間でも、心がリセットされ、翌日からまた母に優しく接することができるようになりました。
タイプ別に違う認知症の症状と接し方の基本知識
認知症と一口に言っても、その種類や症状にはさまざまな違いがあります。もっともよく知られているのはアルツハイマー型認知症ですが、他にもレビー小体型認知症や前頭側頭型認知症(ピック病)などがあります。
たとえば、アルツハイマー型は記憶障害から始まり、徐々に日常生活に支障をきたします。一方、レビー小体型では幻視や筋肉のこわばりが見られたり、前頭側頭型では人格の変化や突発的な行動が目立ったりします。
それぞれに適した対応があるため、症状に応じた接し方を知ることが、介護者の心の負担を軽くするカギとなります。私は医師に相談しながら、母の症状に合ったコミュニケーション方法を少しずつ学んでいきました。
【50代女性のリアル】親の介護と自分の人生を両立する方法
私は50代になってから、ようやく「自分の時間が持てる」と思っていました。子育てが一段落し、仕事にもある程度の見通しがついていたからです。
しかし、現実は違いました。突然始まった母の認知症介護によって、自分の人生設計が大きく変わってしまったのです。
この年代の女性は、親の介護、自身の健康問題、将来への不安など、複数の課題に直面しやすいといわれています。だからこそ、「がんばりすぎない」ことを自分に許すことが大切です。
私は週1回、趣味の習い事に通うようにしました。短い時間でも「自分の人生を生きている」と実感できる時間があると、介護にも前向きに取り組めるようになります。自分を犠牲にしないことは、決してわがままではありません。
介護疲れから自分を守るために実践している習慣と工夫
認知症介護の毎日は、予期せぬことの連続です。常に気を張っていると、心も体も疲弊してしまいます。私はあるとき、ひどいめまいや動悸に悩まされ、医師から「ストレスが限界にきている」と言われました。
それを機に、自分の心と体を整えるための習慣を取り入れるようになりました。
たとえば、
- 朝に白湯を飲む
- ストレッチを5分だけ行う
- 夜寝る前に好きな音楽を聴く
- 週末にひとりで散歩する
といった小さなセルフケアを積み重ねています。
これらは一見些細なことかもしれませんが、継続することで心に余裕が生まれました。介護者自身が健やかでいることが、結果的に良い介護につながるのだと実感しています。
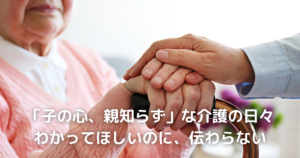
【ブログで心を整理】認知症介護で見つけた小さな逃げ場
介護の中で感じたことをブログに書くようになったのは、まさに「誰かに聞いてほしい」気持ちからでした。
身近な人に話すと、「がんばっているね」と言ってもらえる反面、「大変だね」と返されると、かえって辛く感じてしまうこともあります。でも、ブログでは同じような立場の方と共感し合えることが多く、孤独感が少しずつ和らいでいきました。
書くことで気持ちが整理され、自分の立ち位置を再確認できるようになりました。今ではこのブログが、私にとっての「小さな逃げ場」であり、また新たな自分の居場所にもなっています。
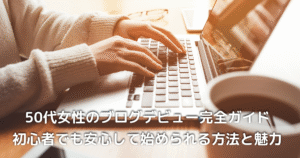
認知症の母と私の今:完璧じゃなくても、大切にしたい日常
介護を始めたころの私は、「完璧にやらなければ」と思い込んでいました。しかし今は、「できることを、できる範囲で」と考えるようになっています。
母は以前のように何でも自分でこなすことはできません。それでも、私の名前を呼んでくれたり、手を握ってくれたりすることがあります。その瞬間に、母との絆が確かにあることを感じるのです。
完璧でなくても、笑顔のある日常があれば、それでいい。
そう思えるようになったのは、介護という長い道のりを歩いてきたからこそです。
【体験記】認知症介護は孤独じゃない。同じ思いのあなたへ
認知症介護は、ときにとても孤独に感じるものです。誰にも理解されないような気持ちになる日もあります。けれど、決して一人ではありません。
この体験を通して私は、多くの人が同じように悩み、葛藤しながら介護に向き合っていることを知りました。そして、悩みながらも「今日をなんとか乗り切ろう」と前を向く姿に励まされました。
このブログを読んでくださっているあなたも、きっと同じような想いを抱えているのではないでしょうか。
その気持ちに、私は心から寄り添いたいと思います。
介護に正解はありません。けれど、ひとりで抱え込まず、時には助けを求めながら、今日という日を少しでも心穏やかに過ごせるよう願っています。
おわりに:認知症介護は「続いていく日常」
認知症介護は、ある日突然終わるものではありません。むしろ、ゆっくりと、でも確実に変化し続ける日常の連なりです。
そのなかで「自分らしく生きること」「自分を大切にすること」を見失わずにいられるよう、私はこれからも模索を続けていきます。
介護に向き合うすべての方に、心からのエールを込めて──。
追記 : 自分を守るために、私が取り入れているサポート
介護は、想像以上に心も体も消耗するものです。
特に私は、夜に母が寝てくれない日が続くと、自分自身の睡眠も浅くなり、イライラや疲労感がどんどん蓄積していきました。
「がんばらないと」と思い続けていた私が、ふと気づいたのは、「自分の体と心を守ることも、介護の一部だ」ということです。
そこで、私が日常に取り入れ始めたのが 睡眠サポートサプリ「グリナ」 でした。
味の素が開発したこのサプリは、睡眠の質を高めてくれると話題で、夜中に何度も起きてしまう私にとっては心強い存在でした。
📌【グリナ(睡眠サポートサプリ)】👇
さらに、母の徘徊が増え始めた時には、GPS見守りタグ「まもサーチ」を使うようになりました。
スマホで位置確認ができるので、「今どこ?」と不安になる時間が大幅に減り、私自身も安心して過ごせるように。
📌【徘徊対策におすすめ】
まもサーチ(GPS見守りサービス)👇
そして、食事の準備が負担に感じる日は、宅配食の「nosh(ナッシュ)」に頼ることもあります。
冷凍で届いてレンジでチンするだけ。栄養バランスもよく、自分の体調管理がしやすくなりました。
📌【忙しい介護生活を少しラクに】nosh(ナッシュ)👇
🌱まとめ
介護はひとりで抱え込まないことが大切です。
頼れるものには頼って、自分を大切にしながら、できるだけ長く穏やかな気持ちで母と向き合っていけたら…そう思っています。
🌿 わたしの楽天ROOM:暮らしの愛用品を更新中
楽天ROOMで見る