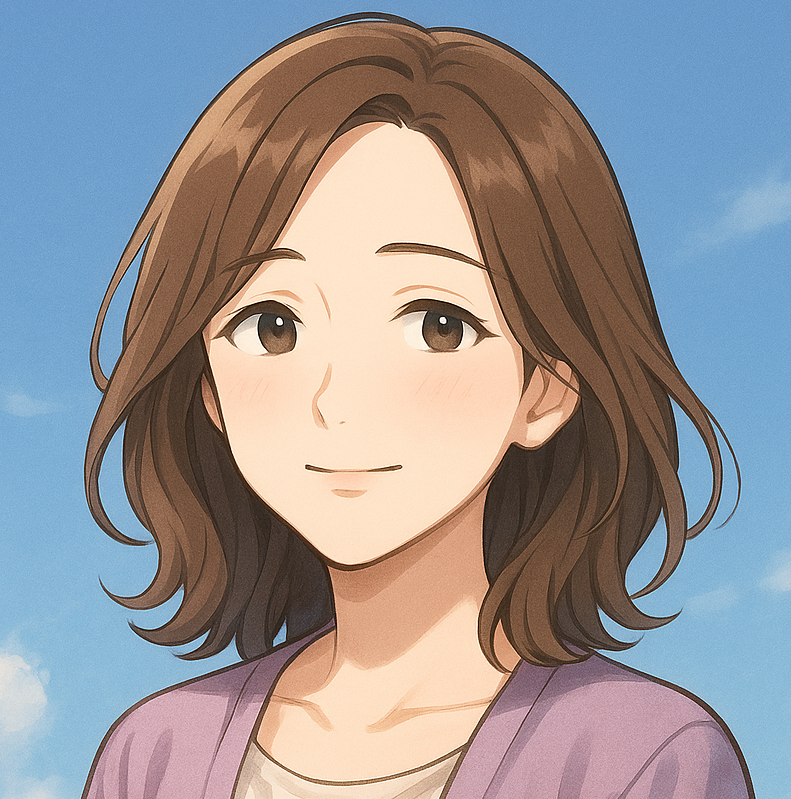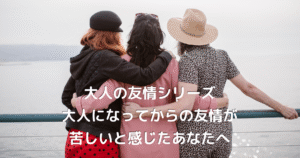子どもが小さかった頃を思い出すと、いつも何かに追われているような毎日でした。
朝起きてから夜寝るまで、まるで回転する歯車のように動き続けていた日々。そんな時期を過ごしてきた方なら、きっと共感していただけるのではないでしょうか。
子育てを経験した多くの方が、いつの間にか身につけてしまう習慣があります。それは「なんでもやりたがり」になってしまうこと。
職場でも、家庭でも、友人関係でも、気がつくと「私がやります」「大丈夫です、任せてください」と手を挙げてしまう自分がいるのです。
ここ数年、私はある大切なことに気づきました。その優しさや責任感から生まれる行動が、実は自分自身を苦しめているということに。
この記事は、私自身が「なんでもやりたがり」から抜け出そうと気づきを得た体験をまとめたものです。
もし同じように悩んでいる方がいたら、「自分を大切にしていいんだ」と思えるきっかけになれば嬉しいです。
同じように他人の目を気にしすぎて疲れてしまう方は、こちらの記事もあわせて読んでみてください。

子育てが育んだ「何でも引き受ける心」の正体
子育てをしていると、自然と身につく習慣があります。
子どもが困っていたら助ける、泣いていたら慰める、何か必要なものがあれば用意する。それは母親として、父親として、とても自然で美しい行動です。
夜中に熱を出した子どもの看病をしながら、翌日の保育園の準備をする。
子どもの機嫌が悪い日は、自分の食事も忘れてあやし続ける。
習い事の送り迎えに、PTA活動、そして仕事。
まるで24時間体制で、誰かのために何かをし続ける日々。
そんな毎日の中で、「相手のことを第一に考える」という思考回路が、深く深く根づいていくのです。
でも問題は、その優しさが時として自分自身を縛ってしまうことがあるということ。
子どもが成長し、手が離れてきても、その「誰かのために何かをする」という習慣は残り続けます。そして気がつくと、家族以外の場面でも同じように振る舞っている自分がいるのです。
職場で残業が必要な仕事があれば、家族との時間を削ってでも「私がやっておきます」と言ってしまう。
友人が悩んでいれば、自分の予定をキャンセルしてでも話を聞いてあげたくなる。
地域の活動やPTAの仕事も、本当は時間的に厳しいとわかっていても、断るのが申し訳なくて引き受けてしまう。
理由は明確です。
長い間、子育てを通して培った「相手を思いやる心」が、私たちの行動の基準になっているから。
でも時として、その美しい心が重荷になってしまうこともあるのです。だからこそ、この習慣の正体をしっかりと理解することが、自分らしい生き方を見つける第一歩になるのかもしれません。
優しさが生み出す見えない疲労感の真実
「なんでもやりたがり」の行動には、確かに美しい動機があります。
誰かの役に立ちたい。
困っている人を見過ごせない。
自分にできることがあるなら、喜んで協力したい。
そんな温かい気持ちが根底にあるからです。
しかし、ここ数年で気づいたことがあります。
その優しさが、知らないうちに自分自身を苦しめているということを。
毎日のように誰かのお手伝いをし、頼まれ事を引き受け、困った人がいれば手を差し伸べる。そんな日々を送っていると、ふとした時に深い疲れを感じることがあります。身体の疲れではなく、心の奥底にある、言葉にしづらい疲れです。
その疲れの正体は何なのでしょうか。
私が思うに、それは「自分を後回しにしてしまう習慣」から生まれているのではないかと思うのです。
子育て中は、自分のことを後回しにするのが当たり前でした。
子どもの食事を先に用意して、自分は残り物で済ませる。
子どもの服を買いに行って、自分の服は何年も前のものを着続ける。
子どもが熱を出せば、自分の体調が悪くても看病に専念する。
そんな日々が当然のように過ぎていきました。
その習慣が、子どもが成長した今でも続いているのです。
誰かのために時間を使い、エネルギーを注ぎ、気持ちを向ける。
そして最後に残った時間とエネルギーで、自分のことをする。
または、もう疲れてしまって、自分のことは明日に回してしまう。
例えば、友人から「今度の休日、子どもの運動会の手伝いをお願いできる?」と頼まれたとします。本当は久しぶりにゆっくりしたかったけれど、「喜んで!」と答えてしまう。
職場で「この企画書、今日中に仕上げてもらえる?」と言われれば、家族との約束があったとしても「大丈夫です」と引き受けてしまう。
一つ一つは小さなことかもしれません。
でも、それが積み重なっていくと、いつの間にか自分自身がエネルギー切れを起こしてしまうのです。
結果として、本当に大切な人たちに対しても、疲れた状態で向き合うことになってしまう。
だからこそ、この優しさと疲労感の関係性を、もう一度見つめ直すことが必要なのかもしれません。
そんな時に大切なのは、ほんの少しでも「自分を休ませる時間」を持つこと。
例えば、香りや空間の力を借りてリラックスするだけでも、心の重さが和らぐ瞬間があります。
▶ アロマデュフューザーで整える、自分だけのリラックスタイム
断ることへの深い罪悪感との向き合い方
「今回は遠慮させてください」
「申し訳ないのですが、お手伝いできません」
そんな言葉を口にするのが、なぜこんなにも難しいのでしょうか。
子育てを経験した多くの方が感じているかもしれませんが、誰かのお願いを断ることに対して、深い罪悪感を感じてしまうことがあります。
「私が断ったら、きっと困るだろうな」
「もしかしたら、私のことを冷たい人だと思われるかもしれない」
「他の人に迷惑をかけてしまうのではないか」
そんな思いが頭をよぎります。
この罪悪感の正体を考えてみると、もしかしたら長い間培ってきた「誰かのために尽くすのが当たり前」という思い込みが関係しているのかもしれません。
子育て中は確かに、子どものためなら自分を犠牲にしても当然という場面がたくさんありました。そしてその経験が、私たちの心に「自分のことよりも、相手のことを優先するのが正しい」という価値観を植え付けてしまったのかもしれません。
でも、よく考えてみると、これは本当に正しいことなのでしょうか。
もちろん、困っている人がいれば助けてあげたいという気持ちは素晴らしいものです。でも、自分の状況や気持ちを無視してまで、常に相手を優先し続けることが、本当に健全な関係性と言えるのでしょうか。
実は、適切に断ることができるということは、相手に対する誠実さの表れでもあるのです。
無理をして引き受けて、結果的に中途半端になってしまったり、疲れ切った状態で対応したりするよりも、正直に「今は難しい」と伝える方が、お互いにとって良い結果を生むことが多いものです。
断ることは決して冷たい行為ではありません。
むしろ、自分の状況を正直に伝えることで、より健全な関係性を築くことができるのです。
だからこそ、この罪悪感を少しずつ手放していく勇気も、時には必要なのかもしれません。
そんな時に役立つのがこちらの記事です。
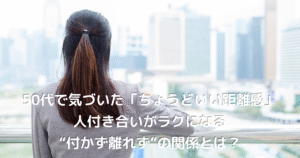
気づきから始まる小さな変化の積み重ね
「自分を苦しめている」ことに気づけたのは、実は大きな前進だったと思います。
なぜなら、気づかないまま同じパターンを繰り返し続けるよりも、立ち止まって自分の行動を見つめ直すことができるからです。
最近は、お誘いや依頼があった時に、すぐに返事をしないように心がけています。
以前の私なら、相手を待たせるのは申し訳ないと思って、その場で「はい、わかりました」と答えていたでしょう。
でも今は、「少し考えさせてください」「明日までにお返事します」そんな風に、一度時間を置いて自分の気持ちと相談する時間を作るようにしているのです。
その短い時間の中で、
「本当に今の自分にできることだろうか」
「引き受けたら、自分の心や体にどんな影響があるだろうか」
「家族との時間は確保できるだろうか」と問いかけてみるのです。
そうすると、意外にも「今回は少し無理かもしれない」と素直に思える場面が多いことに気づきます。
また、断る時の言葉遣いも少しずつ変えています。
「すみません、できません」ではなく、
「ありがとうございます。でも今回は、別のことでお役に立てるかもしれません」というように、感謝の気持ちを込めながら、代替案を提示するようにしているのです。
小さな変化かもしれませんが、こうした積み重ねによって、自分との向き合い方が確実に変わってきています。
以前のように「とにかく引き受けなければ」という焦りではなく、「本当に大切なことを見極めよう」という落ち着いた気持ちで判断できるようになってきました。
だからこそ、まずは気づくことから始めることが、何よりも大切な第一歩なのだと思います。
優しさと自分らしさの調和を見つけて
誰かのために何かをすることは、もちろん素晴らしいことです。
人と人とのつながりの中で、お互いに支え合いながら生きていくのは、とても大切なことだと思います。子育てを通して培った、相手の気持ちに寄り添う力や、困っている人に気づく感受性は、きっとかけがえのない財産です。
ただ、その優しさが自分を消耗させてしまうほどになってしまったら、きっと本来の温かさも失われてしまうのではないでしょうか。
疲れ切ってしまった状態で差し伸べる手よりも、自分も元気で穏やかな状態で差し伸べる手の方が、きっと相手にとっても心地よいものになるはずです。
大切なのは、優しさと自分らしさのバランスを見つけることなのだと思います。
完璧に誰かの期待に応えなくても大丈夫。
時には「できません」と言っても大丈夫。
時には自分の時間を大切にしても大丈夫。
そんな安心感を、自分に与えてあげることも必要なのです。
実際に、少し距離を置いてみると、面白いことに気づきました。
無理をして引き受けていた時よりも、自分が元気な状態で関わることができた時の方が、相手にも喜んでもらえることが多いのです。
エネルギーが充実していれば、より創造的なアイデアを提案できたり、心からの笑顔で接することができたりするからかもしれません。
結果として、自分を大切にすることが、周りの人たちへの本当の思いやりにもつながるのだということを、実感として理解できるようになりました。
新しい「やりたいこと」の発見と向き合う時間
「なんでもやりたがり」から少し距離を置いてみると、思いがけない発見がありました。
今まで「やらなければいけないこと」「頼まれたからやること」ばかりに時間を使っていたのですが、ふと「本当にやりたいこと」が何だったのかを考える余裕が生まれたのです。
長い間、忘れていた趣味のこと。
読みたかった本のこと。
行ってみたかった場所のこと。
学んでみたかった新しいスキルのこと。
友人とゆっくり過ごす時間のこと。
そんな小さな「やりたいこと」が、心の奥底に静かに眠っていることに気づきました。
子育てが忙しかった頃、「自分の時間なんて贅沢」だと思っていました。
でも今思えば、自分が満たされた状態でいることは、決して贅沢なことではないのかもしれません。むしろ、自分が心地よい状態でいることで、家族や周りの人たちともより良い関係を築くことができるのです。
例えば、以前から興味があった陶芸教室に通い始めたり、積読になっていた本を読む時間を作ったり、一人でカフェに行ってゆっくりする時間を持ったり。
そんな小さな「自分時間」を大切にするようになってから、不思議と心に余裕が生まれてきました。
そして、その余裕が、結果的に家族や友人との関係にも良い影響を与えているように感じます。
イライラすることが少なくなり、相手の話をじっくり聞けるようになったり、新しいアイデアを思いついたりすることが増えました。だからこそ、本当にやりたいことを思い出し、それに向き合う時間を作ることも、決して自分勝手なことではないのだと思うのです。
また、体を動かしたり、新しい学びを取り入れることも「やりたいこと」を思い出すきっかけになります。
自宅で気軽に始められるオンラインレッスンなら、無理なく続けられて心も体も整います。
▶ SOELU(ソエル)でヨガ・ストレッチをおうちで体験
今日からできる具体的な一歩を踏み出して
大きく生活を変える必要はないのだと思います。今日からできる小さなことから、少しずつ始めてみればいいのです。
まず、依頼やお誘いを受けた時に、
「少し考えさせてください」と言う習慣をつけること。
そして一人になった時に、自分の心の声に耳を傾けてみる。
「今の自分には、これは重すぎるかもしれない」
「今回は、自分の時間を大切にしたい」
「家族との約束を優先したい」
そんな気持ちを、素直に受け入れてあげるのです。
そして、もしお断りすることになったとしても、それは決して冷たい行為ではないのだということを、自分に言い聞かせてあげる。自分を大切にすることは、結果的に周りの人たちにとっても良いことなのだと信じてみる。
また、週に一回でも、月に一回でもいいので、完全に自分だけの時間を作ってみる。
その時間に、本当にやりたいことをしてみる。
小さなことでもかまいません。
好きなお茶を飲みながら雑誌を読む、散歩をしながら季節の変化を感じる、好きな音楽を聴きながらぼんやりする。そんな時間が、心の栄養になっていくはずです。
小さな変化の積み重ねが、やがて大きな心の余裕につながっていく。そして、その余裕が、本当の意味での優しさや思いやりを育んでいくのだと思います。
温かい関係性を築くための新しい視点
人との関係は、一方的に与え続けることで成り立つものではないのかもしれません。
時には受け取り、時には与える。
時には支え、時には支えられる。
そんな自然な流れの中で、本当に温かい関係性が育まれていくのではないでしょうか。
「なんでもやりたがり」だった自分を責める必要はありません。
それは、長い間誰かを大切に思い続けてきた証拠でもあるのですから。
その優しさや責任感は、きっとこれからも大切な資質として残り続けるでしょう。
ただ、これからは少しだけ、自分のことも同じように大切に思ってあげられたらいいなと思うのです。
子育てという貴重な経験を通して身につけた優しさを大切にしながらも、自分らしいペースで、自分らしい関わり方を見つけていく。
そして、本当に大切な場面では全力で支援し、そうでない時には適度な距離を保つ。
そんなメリハリのある関わり方ができるようになれば、きっとより深く、より持続可能な人間関係を築くことができるのではないでしょうか。
結果として、自分も相手も、お互いに無理をすることなく、自然体で支え合える関係性を育むことができる。
だからこそ、自分を大切にすることから始めてみませんか。
そんな新しい季節の始まりなのかもしれません。
きっと、これまで培ってきた優しさに、新しい智恵が加わって、より豊かな人間関係を築いていけるはずです。
この記事は、子育てを通して身についた「なんでもやりたがり」の習慣を振り返り、自分を大切にする一歩を考えるために書きました。
同じように悩んでいる方が、少しでも心を軽くできるきっかけになれば嬉しいです。
🌸 あなたの「自分時間」におすすめ
🌿 わたしの楽天ROOM:暮らしの愛用品を更新中
楽天ROOMで見る