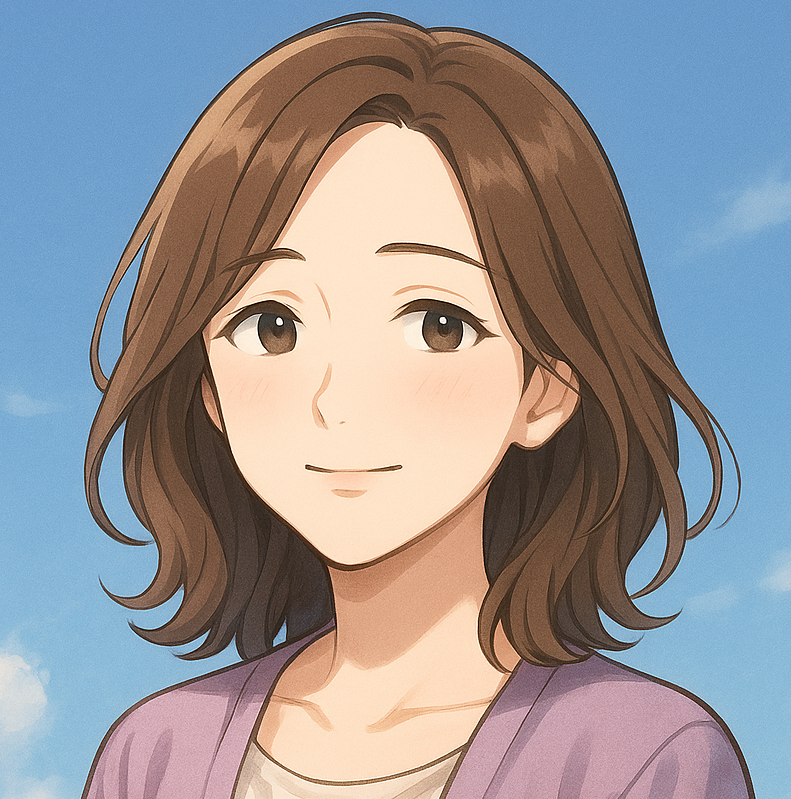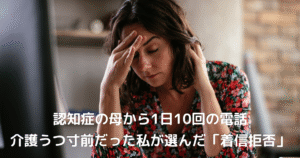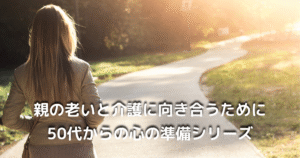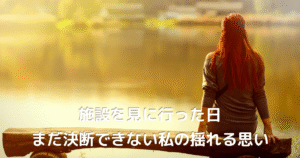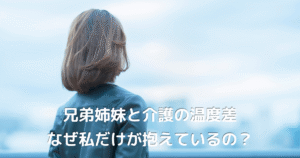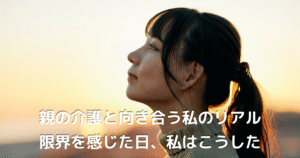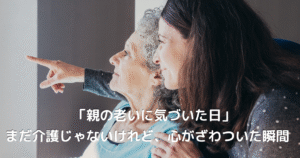親がまだ元気なうちに、介護の話をするなんて縁起でもない――。そう思っていたのは、かつての私です。
でも、ある日突然やってくる”その時”。病気、けが、入院…そんなときにバタバタと始まる介護。情報不足で右往左往しながら、親の希望もわからずに決断を迫られる。「もっと早く話しておけばよかった」と、何度思ったことか。
そんな後悔をしないために、今日は「親が元気なうちにこそ話しておきたい介護のこと」について、実体験を交えてお話ししたいと思います。
突然やってきた”その時”-母の転倒がきっかけで見えた現実
ある日、母が転倒して救急搬送されました。幸い骨折もなく、数日で退院できたのですが、その一件が私たち家族にとっての転機でした。
「今は元気だけど、もしも…」そんな”もしも”は突然やってくるんです。
その時に「何も決めていなかった」「何も知らなかった」では、親も自分も不安だらけになります。救急搬送された病院で、医師から「今後の生活について考えておく必要がありますね」と言われたとき、私は何も答えることができませんでした。
私自身、それまで「介護=まだ先の話」と思い込んでいました。でもいざ現実が目の前にくると、何をどうすればいいのか分からず、ネットで情報をかき集める日々。パソコンの前で夜中まで検索し続けて、結局どの情報が正しいのかもわからず、混乱が深まるばかりでした。
そんな中で、いちばん感じたのは「もっと早く知っておけばよかった…」という気持ち。介護準備は決して難しいことではなく、むしろ知っておくことで心に余裕が生まれるものだと、後になって気づいたのです。
50代だからこそ考えたい介護準備の大切さ
50代という年代は、子育てが一段落し、親の変化も感じ始める時期です。親の足取りが少し重くなったり、物忘れが増えたりと、小さな変化に気づくことも多いでしょう。
この時期は、親もまだ判断力がしっかりしていて、自分の希望や意思を伝えることができます。だからこそ、今のうちに話し合いを始めることが大切なのです。
また、50代の私たちにとっても、介護に関する知識を少しずつ蓄えていくことで、いざという時の精神的な負担を大幅に軽減できます。突然の介護は、想像以上に体力的・精神的な負担が大きいもの。準備があるかないかで、その後の生活の質が大きく変わってくるのです。
ちょっと立ち止まって、自分の暮らしや人生を見つめ直したいと感じた方へ。
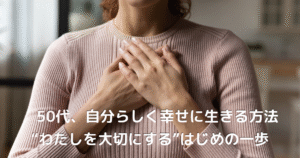
ステップ①:地域の相談窓口を知っておく-最初の一歩は情報収集から
まず、情報収集から始めましょう。地域には”地域包括支援センター”という、高齢者や家族の相談に乗ってくれる窓口があります。
私はここで、介護サービスの仕組みや、要介護認定の流れなどを教えてもらいました。「今すぐじゃなくても、こういう制度があるんだ」と知っておくだけでも、大きな安心になります。
最初は「まだ必要ないかもしれないのに相談していいのかな」と遠慮していましたが、思い切って家の近くのセンターに電話をしてみました。「まだ介護が必要というわけではないんですが…」と伝えたら、「今のうちに話を聞きに来るのは、とても大切なことですよ」と、丁寧に話を聞いてくださいました。その言葉が、すごく心に残っています。
地域包括支援センターでは、介護保険の申請方法から、地域の介護施設の情報、家族の心のケアまで、幅広く相談に乗ってくれます。また、定期的に介護に関する講座や勉強会も開催しているので、同じような状況にある方々と情報交換することもできます。
センターの職員さんは、みなさん豊富な経験を持っていて、「こんなケースもありますよ」と具体的な事例を交えて説明してくれます。一人で悩むより、専門家に相談することで、ずっと心が軽くなりました。
ステップ②:介護が必要になったときの流れを理解する
介護が始まる流れは、大きく分けて要介護認定の申請、ケアマネジャーとの面談、サービス利用の開始という3つのステップがあります。
これを知らずに、いきなり「デイサービスってどうやって申し込むの?」「費用は?」と焦ってしまう人が多いんです。私も母の時、何も知らずに役所に電話し、たらい回しにされた苦い経験があります。あのときの混乱は、今思い出しても胃が痛くなりそうです。
要介護認定は、市区町村の窓口で申請します。申請後、認定調査員が自宅を訪問し、本人の状態を確認します。この時、家族が立ち会って、普段の生活の様子を詳しく伝えることが大切です。
認定が下りると、ケアマネジャーという介護の専門家が付き、どのようなサービスを利用するかを一緒に考えてくれます。ケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きながら、最適なケアプランを作成してくれる、とても頼りになる存在です。
最近では、スマホやパソコンから市区町村のホームページを見れば、ある程度の情報は得られます。でも、書かれている内容が専門用語だらけで分かりづらいことも。そんな時は、直接相談できる窓口が本当にありがたい存在でした。
また、介護保険の自己負担割合や、高額介護サービス費の制度なども、事前に知っておくと安心です。介護にかかる費用は、所得によって1割から3割の自己負担となりますが、月額の上限が決められているので、極端に高額になることはありません。
ステップ③:介護サービスの種類を詳しく知る
訪問介護、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム…。名前は聞いたことがあっても、実際の違いや使い方って意外と知らないものです。
訪問介護は、ヘルパーさんが自宅に来て、身体介護や生活援助をしてくれるサービスです。入浴やトイレのお世話から、掃除や買い物まで、様々なサポートを受けることができます。住み慣れた自宅で過ごし続けたい方には、とても心強いサービスです。
デイサービスは、日中の時間を介護施設で過ごすサービスです。入浴やレクリエーション、リハビリなどを通じて、他の利用者さんとの交流も楽しめます。家族にとっても、その間に仕事や家事をこなすことができる、貴重な時間となります。
ショートステイは、数日から数週間、介護施設に泊まりがけで滞在するサービスです。家族が旅行に行ったり、体調を崩したりした時に利用できます。また、将来的に施設入所を考えている場合の「お試し」としても活用できます。
私たちも実際に3施設ほど資料を取り寄せて、母と一緒に見比べながら話しました。「ここなら近いし、通えそう」と、自分の口で話してくれたのが何より嬉しかった。
見学にも行きました。スタッフの雰囲気、利用者さんの表情、施設のにおい――。パンフレットでは分からない「現場の空気」を肌で感じることができたのは大きな収穫でした。そのとき母が「ここなら安心できそう」と言ったのを今でも覚えています。その一言で、私の心もスッと軽くなったのです。
施設見学の際は、食事の時間に合わせて訪問するのもおすすめです。食事の内容や、利用者さんがどのように過ごしているかを見ることで、施設の雰囲気がよくわかります。また、スタッフの方に質問することで、どのような理念で運営されているかも理解できます。
ステップ④:家族の役割を話し合っておく-みんなで支える介護
「誰が中心になるか」「金銭的な負担はどうするか」
これは、できれば家族全員で話し合っておきたいポイントです。介護は、ひとりにすべてがのしかかると本当に大変です。
うちは二人兄妹ですが、最初は「面倒みれるのは長女のあなただからよろしく」と言われ、内心モヤモヤしていました。でも、後から冷静に話し合って、できることをそれぞれが分担したことで気持ちもぐんと楽になりました。
兄弟姉妹がいる場合、住んでいる場所や仕事の状況、家族構成によって、できることも違ってきます。近くに住んでいる人が日常のケアを担当し、遠方に住んでいる人は金銭的な支援や月に一度の通院同行など、それぞれの状況に応じた役割分担を決めておくことが大切です。
介護に限らず、家族の問題は「話し合うこと」自体が難しいと感じる方も多いと思います。でも、話してみると「意外と受け入れてくれる」「協力しようとしてくれていた」なんてこともあるんですよね。
話すタイミングは、例えば親の誕生日やお正月など、家族が集まりやすい時期に少しずつ切り出すのもおすすめです。いきなり重い話題を持ち出すのではなく、「最近、○○さんのお母さんが介護を受けることになったんだって」といった具合に、身近な話題から入ると話しやすくなります。
また、家族会議のような形で改まって話し合うのも良いですが、お茶を飲みながら、散歩をしながらなど、リラックスした雰囲気で話すことも大切です。緊張した雰囲気だと、本音を言いにくくなってしまいます。
家族との信頼関係に悩んだとき、心を整えるヒントになる記事です。
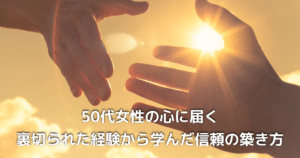
ステップ⑤:親の「想い」を聞いておく-何より大切なのは本人の意思
そして何より大切なのが、”親の気持ち”。どこで、どんなふうに過ごしたいか。延命治療はどうしたいか。お金のことは?正直、面と向かっては聞きづらいことばかりです。でも、聞かずに進めるのはもっとつらい。
私は、エンディングノートを渡して、母と一緒に書きながら話す時間を取りました。「ここに書いてあるのを読んでおいてね」と母に言われたとき、少しホッとしたのを覚えています。
エンディングノートは、本人の意思を残せるだけでなく、家族の心の整理にもつながります。親の本音に触れたとき、「この人も、ちゃんと人生を考えていたんだな」と、ちょっと泣きそうになりました。
親の想いを聞く時は、一度にすべてを聞こうとせず、少しずつ時間をかけて話すことが大切です。「もし体が不自由になったら、どこで暮らしたい?」「好きな食べ物は何?」といった日常的な質問から始めて、徐々に深い話題に入っていくと自然です。
また、親の若い頃の話を聞くことで、その人の価値観や大切にしていることがわかります。どんな人生を歩んできたのか、何を大切にして生きてきたのかを知ることで、介護においても本人の意思を尊重した選択ができるようになります。
親の想いを聞く過程で、親子の関係も深まります。普段は照れくさくて言えないような感謝の気持ちを伝えたり、子どもの頃の思い出話をしたりすることで、お互いの理解が深まります。
在宅介護と施設介護-それぞれのメリットとデメリット
介護方法には、大きく分けて在宅介護と施設介護があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが良いかは家族の状況や本人の希望によって変わってきます。
在宅介護のメリットは、住み慣れた環境で過ごせることです。長年住んでいる家は、本人にとって最も安心できる場所。家族と一緒に過ごす時間も多く、これまでの生活リズムを大きく変えることなく介護を受けることができます。
一方で、家族の負担が大きくなりがちなのがデメリットです。24時間体制でのケアが必要になった場合、家族だけでは対応が難しくなることもあります。また、家の中をバリアフリーにリフォームする必要が出てくることもあります。
施設介護のメリットは、専門的なケアを24時間受けられることです。医療的なケアが必要になった場合も、看護師や医師が常駐している施設なら安心です。また、同世代の方々との交流や、様々なレクリエーション活動を通じて、生活に張り合いを持つことができます。
デメリットとしては、環境の変化に適応するのが大変なことや、費用がかかることが挙げられます。特に、これまで家族中心の生活を送ってきた方にとっては、集団生活に慣れるまでに時間がかかることもあります。
介護費用の準備と支援制度の活用
介護にかかる費用は、多くの方が心配される点です。介護保険を利用すれば、サービス費用の1割から3割の自己負担で済みますが、それでも月数万円の出費となることが多いです。
在宅介護の場合、訪問介護やデイサービスを利用すると、月2万円から5万円程度の自己負担が一般的です。介護度が高くなるほど、利用できるサービスの上限額も高くなります。
施設介護の場合は、施設の種類によって費用が大きく異なります。特別養護老人ホームなら月10万円程度から、有料老人ホームなら月20万円以上かかることもあります。
費用の準備方法としては、介護保険以外の民間の介護保険に加入する、貯蓄を計画的に行う、住宅ローンを早めに完済して家計負担を軽くするなどの方法があります。
また、高額介護サービス費という制度もあります。これは、1か月の介護サービス利用料が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。所得に応じて上限額が決められているので、極端に高額な負担になることはありません。
介護する側の心のケア-燃え尽きないために
介護は、思っている以上に精神的な負担が大きいものです。親の変化を受け入れることの辛さ、将来への不安、兄弟姉妹との関係など、様々な悩みを抱えることになります。
介護する側が燃え尽きてしまわないよう、適度な息抜きや相談相手を持つことが大切です。地域の家族会に参加したり、介護経験者の話を聞いたりすることで、「自分だけではない」と感じることができます。
また、完璧を求めすぎないことも大切です。「親に良い介護をしてあげたい」という気持ちは素晴らしいものですが、自分の生活を犠牲にしてまで頑張りすぎると、長続きしません。
ときには、介護サービスを利用して自分の時間を作ったり、兄弟姉妹に代わってもらったりすることも必要です。介護する側が健康でなければ、良い介護はできません。
がんばりすぎてしまう自分に気づいたら、ぜひ読んでみてください。

地域とのつながりを大切に
介護は、家族だけで抱え込むものではありません。地域の方々の理解と協力があってこそ、安心して介護を続けることができます。
ご近所の方々に、家族の状況を説明しておくことで、緊急時に助けてもらうことができます。また、地域の見守りサービスや配食サービスなどを利用することで、一人暮らしの時間も安心して過ごすことができます。
民生委員の方や、地域の老人会、町内会など、様々な組織が高齢者の生活を支援しています。こうした地域資源を活用することで、介護の負担を軽減することができます。
技術の活用も視野に入れて
最近では、介護に役立つ様々な技術が開発されています。見守りセンサーや服薬管理システム、コミュニケーションロボットなど、介護の質を向上させる技術が身近になってきています。
こうした技術を活用することで、離れて暮らしていても親の安全を確認できたり、薬の飲み忘れを防いだりすることができます。全てを人の手で行う必要はなく、技術に頼れる部分は頼ることで、より良い介護を実現できます。
最近では、ソニーの「MANOMA(マノマ)」のように、室内の動きを検知してスマホに通知してくれる見守りサービスも登場しています。離れて暮らすご家庭でも、日々の生活リズムや異変にいち早く気づけるので、安心感が違います。
おわりに:未来の自分のために
介護は、ただの「手助け」ではなく、人生の一部になります。だからこそ、親が元気なうちに”準備”という名の安心を、少しずつ積み重ねていくことが大事だと思うのです。
最初は「話しにくい」と感じることもあるかもしれません。でも、一歩ずつでいいんです。ひとつ、またひとつと準備していくことで、不安は少しずつ安心へと変わっていきます。
介護の準備は、親のためだけではありません。いつか自分も年を取り、誰かのお世話になる日が来るでしょう。その時のためにも、今から介護について学び、準備をしておくことは、とても意味のあることです。
また、介護を通じて、親との関係が深まることもあります。これまで言えなかった感謝の気持ちを伝えたり、親の人生の話を聞いたりすることで、新たな親子関係を築くことができます。
50代の今だからこそ、親も自分も元気なうちに、ゆっくりと時間をかけて準備を進めていきましょう。いま動き出せば、きっと未来の自分が「ありがとう」と言ってくれる。そんな気がしています。
介護は決して一人で背負うものではありません。家族、地域、専門家、そして様々な制度やサービスが、みなさんを支えてくれます。不安になったときは、一人で悩まず、まずは相談してみることから始めてください。
きっと、思っていたより多くの人が、あなたと同じ想いを抱えていることがわかるはずです。そして、その人たちとともに、親にとっても、自分にとっても、最良の介護を実現していけるのです。
🧰 介護準備に役立つおすすめグッズ
📘 親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと
実際に介護が始まったとき、すぐ役立つノウハウが詰まった実用書。体験ベースで書かれていて、初心者にも読みやすい構成です。
📘 一番わかりやすい エンディングノート
親の希望を整理し、家族みんなが安心できる一冊。「何をどう書けばいいのか」が明確で、親子で話しながら書くのにぴったりです。
📡 MANOMA(マノマ)|ソニーの見守りサービス
離れて暮らす親の見守りにおすすめ。スマホで生活リズムを確認でき、何かあった時の安心感につながります。
📚 こちらの記事もおすすめです
🌿 わたしの楽天ROOM:暮らしの愛用品を更新中
楽天ROOMで見る