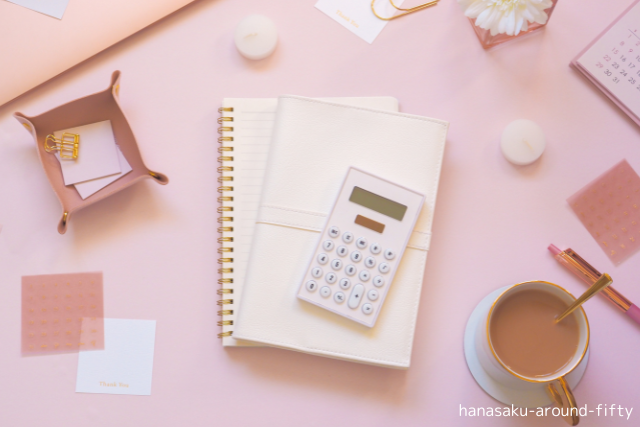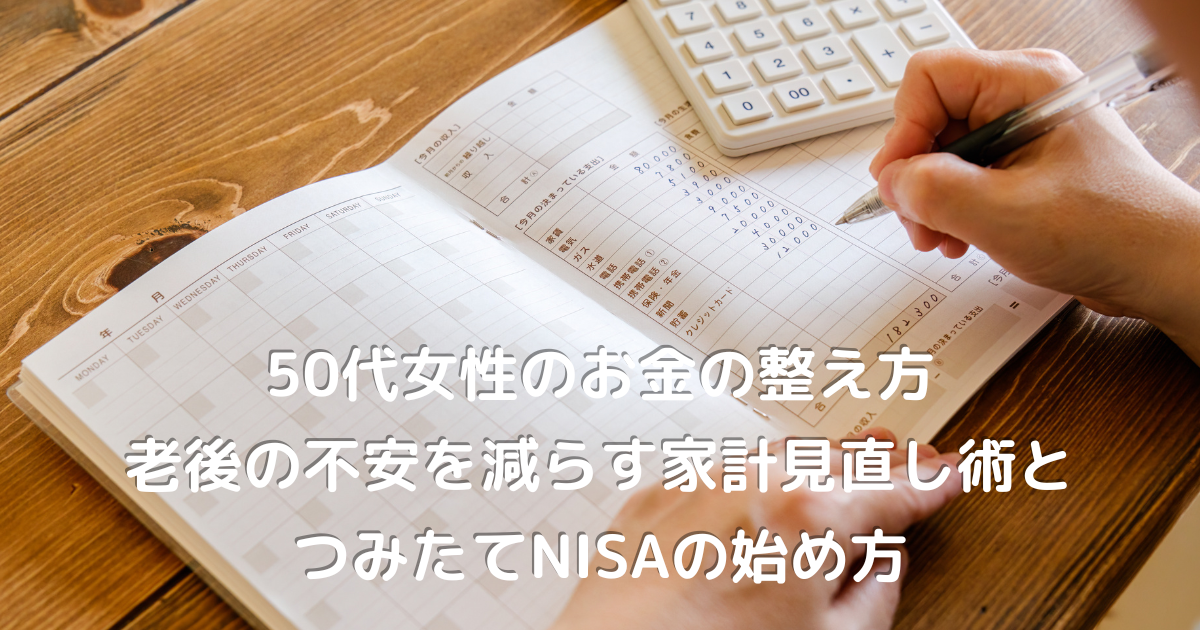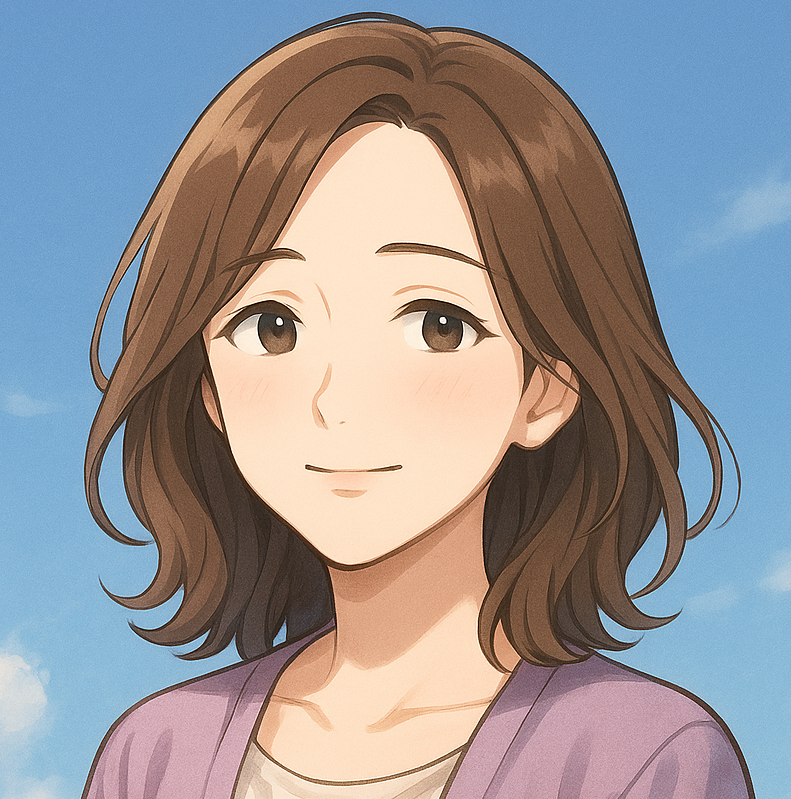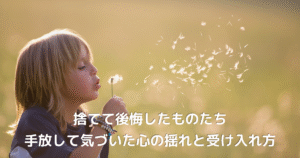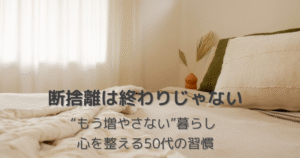誰にも言えない「お金の不安」を抱えるあなたへ
「老後、私、やっていけるのかな」
50代になってから、そんなふうに思うことが増えました。スーパーで値札を見つめながら、通帳記帳をしながら、夜中にふと目が覚めたとき。特別な理由があるわけでもないのに、心の奥からじわりと湧き上がるあの感情。
もしこの先、病気になったら?仕事を辞めることになったら?両親に介護が必要になったら?大きな不安ではありません。けれど、じわじわと効いてくる。小さな棘のように、ずっと心のどこかに刺さったままになるような、そんな気持ちです。
実は、内閣府の調査によると、50代女性の約7割が老後の生活に不安を感じています。私だけじゃなかった。同じような想いを抱えている女性が、こんなにもたくさんいるのだと知って、少しほっとしたのを覚えています。
でも同時に思ったのです。みんな一人で抱え込んでいるんだな、と。職場でも、友人との集まりでも、お金の話はなかなかできません。「貯金、どれくらいある?」なんて、親しい友人にも聞けませんよね。
私たち50代女性には、特有の事情があります。子どもの教育費がまだかかる、住宅ローンが残っている、親の介護が始まりそう、更年期で体調が不安定、職場でのポジションが微妙…。20代、30代の頃とは違う複雑な状況の中で、お金と向き合わなければならないのです。
同じように感じているあなたへ。この先の暮らしに、少しでも安心を増やすヒントを、この記事に詰め込みました。いっしょに「整える」第一歩を踏み出しませんか?
老後資金は「増やす」より「整える」ことから
世の中には、「老後資金は2000万円必要です」とか、「今すぐ投資を始めましょう!」という情報があふれています。テレビをつければ資産運用の特集、本屋に行けば投資本がずらり。SNSでは「主婦でも月10万円稼げる」という広告が次々と流れてきます。
でも、そんな情報を見るたびに、私は焦りと不安を感じていました。「みんなはもっと賢くお金を管理しているのに、私だけが取り残されている」そんな気持ちになったのです。
もちろん、お金を”増やす”ことは大切です。けれど、私が本当に欲しかったのは、「安心して暮らせる感覚」でした。誰かの言う正解ではなく、自分の暮らしに合った、お金との付き合い方。
その答えを見つけるには、「整える」という視点が必要だと気づいたのです。整えるとは、ただ節約することでも、我慢することでもありません。自分にとって大切なものを見極め、無理のない形で暮らしを見つめ直すこと。お金を使うことに罪悪感を抱くのではなく、心を軽くするように使っていくことです。
私は「お金を整える」ことで、はじめて心の余白を感じるようになりました。毎月の支出に怯えることもなくなり、たまの外食や新しい服を買うときも、「これは私が選んだこと」という納得感があるようになったのです。
まずは「何にお金を使っているか」を知ることから
私が最初に向き合ったのは、「自分が何にどれだけ使っているか」でした。正直、長い間なんとなくで暮らしてきました。家計簿は3日坊主。レシートは財布に溜まり、見て見ぬふりをしていた日々。クレジットカードの明細も、「今月は使いすぎたな」と思いながらも、詳しく見ることはありませんでした。
でも、それでは不安が増すばかりでした。「これじゃ足りないかもしれない」と思いながらも、どこにいくら使っているのか、具体的には把握していなかったのです。
だから、まずはノートを一冊用意して、ひと月の支出をざっくり書き出してみました。完璧である必要はありません。思い出せる範囲で、だいたいの金額で構いません。
毎月必ず支払う固定費として、住居費、保険料、通信費、光熱費。月によって変わる変動費として、食費、日用品、医療費、交通費、交際費。そして50代特有の支出として、家族関連費、美容健康費、冠婚葬祭費、突発的な医療費、家のメンテナンス費用。
最初にこの書き出しをしたとき、予想以上に多くの項目があることに驚きました。特に「50代特有の支出」は、若い頃にはなかった出費が多く、これが家計を圧迫している大きな要因だったのです。
すると、不思議なことに、「なんとなくの不安」が「見える安心」に変わっていくのを感じました。「わからない」から「見えている」に変わるだけで、こんなにも心が軽くなるものなのですね。
家計簿を続けるコツは、完璧を求めないことです。1円単位で合わせる必要はありませんし、毎日つけようとしなくても大丈夫。アプリを使ってレシートを撮影するだけでも十分です。大切なのは、「私のお金はこんなふうに使われているんだ」ということを知ることなのです。
節約より大切な「自分らしいお金の使い方」を見つける
支出を見直す中で、私は自分が「何に価値を置いているか」に気づきました。外食は控えても、コーヒー豆は少しいいものを選びたい。洋服は最低限でいいけれど、肌着や寝具にはこだわりたい。旅行は行かないけど、季節の花を飾ることはやめたくない。美容院の頻度は減らしても、スキンケアは手を抜きたくない。
お金の使い方って、自分の価値観がまるごと映るんですね。だから私は、節約よりも「選ぶこと」を大切にしようと思いました。削るのではなく、整える。我慢ではなく、納得して使う。それが、自分の中の安心感に繋がっていくのだと感じました。
友人のAさんは「本には絶対にお金をかける」と言います。月に1万円以上本を買うけれど、服は年に数着しか買わない。彼女にとって、本は心の栄養だから、ここは削りたくないのだそうです。一方、Bさんは「美味しいものを食べることが一番の幸せ」と話します。食費は他の人より高めかもしれないけれど、その分、娯楽費や物にかけるお金は最小限に抑えています。
正解なんてないのです。大切なのは、自分が何に価値を感じるかを知ること。そして、その価値観に沿ってお金を使っていくことなのだと思います。
「これがないと生活の質が下がる」と感じるものは何でしょうか。「これにお金をかけると心が豊かになる」と感じるものは何でしょうか。そして「これは他の人と比べて多めに使っている」と感じるものは何でしょうか。それがあなたの价値観の現れです。罪悪感を感じる必要はありません。
老後資金の「2000万円神話」に惑わされない現実的な考え方
老後資金について考えるのは、誰にとっても重いテーマです。正直に言えば、私も最初は怖かった。「こんなに貯金が少なくて、大丈夫なんだろうか」と。でも、よくよく調べてみると、「老後資金は2000万円必要」というのも、すべての人に当てはまる話ではないことがわかってきました。
この「2000万円」という数字は、あくまで平均的なモデルケースを基にしたもの。夫婦2人世帯で、持ち家があり、年金額が一定水準以上ある場合を想定しています。住まいの形、家族構成、年金額、健康状態。一人ひとり違うからこそ、「私の暮らしには、いくら必要なのか」を自分自身の視点で見つめていくことが大切なんです。
まず、「老後、月にいくらあれば安心して暮らせるか?」という目安を立ててみました。現在の支出を把握して、老後になると不要になる費用、住宅ローンや教育費などを引き、増える費用、医療費や介護費用などを加えます。一般的には、現役時代の7割程度が目安とされています。
次に、「ねんきんネット」で将来もらえる年金の概算額を確認します。思っていたより多い場合も、少ない場合もあります。まずは現実を知ることから始めましょう。そして、月々の生活費から年金額を引いた金額が、自分で準備すべき金額です。これに老後の年数をかけると、必要な老後資金の目安がわかります。
私の場合、現在の支出が月25万円、老後の予想支出が月20万円、予想年金額が月15万円でした。つまり、月5万円の不足。これを20年間で考えると1200万円。「2000万円より少ないじゃない」と、少しほっとしたのを覚えています。
もちろん、病気や介護などの予期せぬ出費に備えて、余裕を持った計画を立てることは大切です。でも、「絶対に2000万円ないとダメ」と思い込んで、無理な節約や投資に走る必要はないのです。
50代からでも間に合う、つみたてNISAという選択肢
金融庁が選んだ安心な投資信託の中から選べて、非課税で運用できる「つみたてNISA」は、50代からでも無理なく始められる心強い味方です。
お金を増やすことに自信がなかった私でも、始めやすかったのが「つみたてNISA」でした。難しそうなイメージがあったけれど、調べてみると、月に100円から始められるし、長期で運用することで、少しずつ資産を育てていける仕組み。金融庁が選定した投資信託の中から選ぶので、極端にリスクの高い商品を選んでしまう心配もありません。
大切なのは、今できる範囲で、できることから始めるということ。つみたてNISAなら、運用益が最長20年間非課税になりますし、いつでも解約・引き出しが可能です。老後資金だけでなく、急な出費にも対応できるのが安心でした。
注意点もあります。投資ですから、元本割れのリスクがありますし、短期での利益は期待できません。でも、長期で考えれば、預貯金だけでは追いつかないインフレにも対応できる可能性があります。
私は最初、月5000円から始めました。コーヒー代を少し我慢すれば捻出できる金額です。「投資」なんて大げさなものじゃなくてもいい。将来の自分を、少しだけ助けてあげるための”種まき”だと思えば、なんだか優しい気持ちになれました。
始めて2年が経ちましたが、市場の上下に関係なく、毎月決まった日に決まった金額が投資されていく安心感があります。毎日値動きをチェックする必要もなく、年に数回、運用状況を確認するだけ。これなら私にも続けられそうです。
初心者には、全世界株式インデックスファンドがおすすめです。これ1本で、世界中の株式に分散投資できるので、リスクを抑えながら、長期的な成長が期待できます。信託報酬が年0.5%以下のものを選ぶと、コストも抑えられます。
つみたてNISAについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
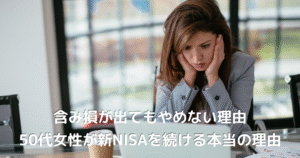
保険を見直して、家計に余白をつくる
50代になると、保険の見直しも大切な家計管理の一部です。若い頃に入った保険をそのまま続けている方も多いと思いますが、ライフステージが変わると、必要な保障も変わってきます。子どもが独立すれば、高額な死亡保障は不要になりますし、逆に、病気のリスクが高くなるので、医療保障を充実させる必要があるかもしれません。
生命保険の死亡保障については、子どもが独立したら、葬儀費用程度の200~300万円があれば十分です。住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険で保障されますから、それほど心配する必要はありません。
一方で、医療保険やがん保険は充実させたいところです。50代以降はがんのリスクが高くなりますし、治療も通院が中心になることが多いので、通院保障があると安心です。診断給付金があれば、治療費以外の支出にも対応できます。
個人年金保険も、老後資金の準備として有効です。税制優遇がありますし、確実に積み立てができます。ただし、インフレリスクには注意が必要です。
私は保険の見直しで、月々の保険料を1万円削減できました。不要な保障を削り、本当に必要な保障を充実させることで、家計の負担を軽くしながら、より安心できる保障を得ることができたのです。
最近は無料のオンライン保険相談も増えていて、自宅にいながら気軽に話せるサービスも充実しています。迷っているなら、一度だけでも話を聞いてみる価値はあると思います。
無理しない仕組みづくりで、お金の管理を「習慣」に
家計を整えるために、私は「工夫」に目を向けました。意志に頼ると、疲れてしまいます。「今月は絶対に節約する!」と決意しても、疲れた日にコンビニで余計なものを買ってしまったり、ストレスで衝動買いをしてしまったり。そんな自分を責めて、また落ち込む…という悪循環に陥りがちでした。
だから、自然に整う仕組みを少しずつ取り入れました。まず、お金の流れを整えることから始めました。使うお金と貯めるお金の口座を分けて、給与が入ったら、まず貯金分を別口座に移します。予算制の電子マネーを活用して、月初に決まった金額をチャージし、現金感覚で使います。現金は週に1回、決まった金額だけ引き出すようにしました。
支出をコントロールするために、「ごほうび予算」をあらかじめ設定しました。月に5000円など、罪悪感なく使える予算を確保することで、ストレス発散も計画的にできるようになります。買い物前にはリストを作成し、スーパーの特売日を把握して、計画的に買い物をするようになりました。
家計管理を習慣化するために、月1回の「お金のリセット日」を設けました。家計の見直しと、翌月の予算立てをする日です。レシートは溜め込まずに、すぐに家計簿アプリに入力します。年に1回は、保険や通信費などの固定費をチェックします。
将来への備えも自動化しました。冠婚葬祭や旅行など、年に数回の大きな出費に備えて積立をします。つみたてNISAや定期預金を自動で積み立てる設定にします。家計簿アプリを活用して、銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で家計簿を作成します。
ちょっとしたことだけれど、暮らしが整っていく実感がありました。何より、「頑張らなくても自然にできる」というのが、私には合っていました。
家計を見直す第一歩として、手書きで支出を「見える化」するのもおすすめです。
📘 ハイタイド 家計簿ノート(Amazon)
一人暮らしだからこそ大切な、将来への備え
単身世帯だからこそ、老後への備えはより重要になってきます。パートナーがいる家庭と違って、一人ですべてを管理し、決断していかなければなりません。でも、その分、自分のペースで、自分の価値観に合わせて、お金を整えていくことができるのも確かです。
単身世帯の場合、老後に必要な生活費は夫婦世帯よりも割高になることが多いです。家賃や光熱費などの固定費を一人で負担するためです。また、病気や介護が必要になったときの備えも、より具体的に考えておく必要があります。
しかし、悲観的になる必要はありません。単身世帯だからこその強みもあります。家族の意見に左右されず、自分の判断で投資や保険を選べること。支出をコントロールしやすいこと。急な変化にも柔軟に対応できることなどです。
私が単身世帯として特に意識していることは、緊急時資金の確保です。病気で働けなくなったときのために、生活費の6か月分は預貯金で確保しています。また、将来的に住まいをどうするかも重要な検討事項です。持ち家を維持するか、住み替えるか、老人ホームなどの選択肢も含めて考えています。
健康管理にも一層気を配るようになりました。医療費を抑えるためというより、自分の生活の質を保つためです。定期健診は欠かさず、運動習慣も続けています。これも、将来への大切な投資だと考えています。
「安心できるお金」とは、自分で選べる暮らしのこと
お金に関する一番の安心って、「これだけ使っても大丈夫」と、自分で決められることだと思います。誰かの目を気にせず、情報に惑わされず、自分の暮らしを、自分のリズムで整えること。
たとえば、私は月に一度、「お金のリセット日」と称して、お財布の中身を全部出す時間を作っています。いま、どれだけあるか。どこに使ったか。そして、「今月はどうしたいか」を自分に聞いてみる。それだけで、また一歩、お金と仲良くなれたような気がするんです。
この習慣を始めてから、お金に対する見方が変わりました。以前は「足りない、足りない」と思っていたのが、「今月はこれだけ使えるから、何に使おうかな」と考えるようになったのです。制限ではなく、選択肢として捉えられるようになりました。
お金の安心感を高めるためには、まず現状を把握することから始めます。今の収入と支出を正確に知り、将来の計画を立てます。老後に必要な金額を具体的に計算し、月1000円の節約でも、自分を褒めてあげます。一人で悩まず、専門家に相談したり、同じような状況の友人と情報交換をしたりすることも大切です。
お金の安心感は、一朝一夕には身につきません。でも、小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな安心感につながっていくのです。
一人で抱え込まないで、相談できる場所があります
「お金の悩みは、人に話しにくい」それはとてもよくわかります。でも、ひとりで抱え込む必要なんて、本当はないんです。信頼できる友人や、家族。あるいは、プロのファイナンシャルプランナー。話すことで、心がすっと軽くなることがあります。
私は以前、勇気を出して無料のマネー相談に申し込んだことがあります。専門家の話を聞いて、「そんなに心配しなくても大丈夫」と言われたとき、長い間肩に載っていた重荷が少し軽くなったような気がしました。
家計の見直しを一人で進めるのが不安な場合、投資や保険について詳しく知りたい場合、老後資金に大きな不安がある場合は、ファイナンシャルプランナーに相談することをお勧めします。初回相談は無料の場合が多いので、気軽に活用してみてください。
今の暮らしを見つめて、できることからでいいんです。家計簿アプリをダウンロードする、レシートを整理してみる、つみたてNISAを調べてみる…。その一歩が、あなたのこれからを変えていきます。
また、同じような状況の女性たちとのつながりも大切です。お金の話は デリケートですが、信頼できる友人同士なら、お互いの経験や知恵を共有することができます。一人で悩んでいたことが、実は多くの人が抱える共通の悩みだったりするものです。
50代からの家計見直しは、決して遅くありません。むしろ、経験と知識を活かして、より効率的に資産を築くことができる年代です。「お金の不安」は「お金の安心」に変えることができます。一歩ずつ、あなたのペースで進んでいきましょう。
あなたの豊かな老後のために、今日から始められることがあります。小さな一歩が、大きな安心につながっていくのです。そして何より、あなたは一人ではありません。同じような思いを抱える仲間がいて、支えてくれる専門家がいて、一緒に歩んでくれる家族がいます。安心して、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
📚 お金を整えるためのおすすめアイテム
🌿 わたしの楽天ROOM:暮らしの愛用品を更新中
楽天ROOMで見る📚 あわせて読みたい関連記事